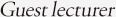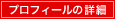A.C.P.C.提携講座 ライブ・エンタテインメント論
提携講座/登壇講師インタビューseason 3
CHAPTER.1
シンセサイザーは楽器ではなかった?
― 講義では演奏家の権利関係も含め、「ミュージック・シンセサイザー 音楽に果たすべきもの」というテーマでお話を頂きました。400名近い学生が受講しましたが、松武先生から見て学生たちはいかがでしたか?
松武秀樹さん(以下松武と敬称略):皆さん、目が輝いていていいですね。僕はシンセサイザーをやっていまして、ミュージシャンですので、これまでの経験をもとに日本の音楽産業を支えていく演奏家を育てなければならないと思っています。
テクノロジー・ミュージックの完成形はその時代時代が認めるもので、時が進めば新たなテクノロジーが誕生して進化が始まります。そこで忘れてはならないのは、終わりなき追求です。
その為にも、これからの演奏家のいろいろな権利を支えて、彼らが創るものに対してちゃんとした対価が払われていくことが重要です。今日は学生にこのことも伝えられたと思っています。
― 松武先生は、音楽の配信会社(株)ミュージックエアポートの代表でもあり、また、日本芸能実演家団体協議会で演奏家の権利守る活動をなさっていますが、どのようなきっかけからですか?
松武:それは、1994〜95年頃に、シンセサイザーは楽器か?という論議から始まっています。当時アナログシンセサイザーは音色の記憶ができなかった。しかし、ICの技術がだんだんと進歩して記憶装置が確立され、例えば僕がいま創った音を3日後に同じ音で再現できるようになった。
― シンセサイザーは楽器として、認められていなかったのですね。
松武:生楽器のピアノやギターなどは、ミュージシャンの身体に接合して演奏がなされています。著作権、隣接権の定義では身体に接合していることが凄く重要なのですが、シンセサイザーはPLAYボタンを押した瞬間に、手から離れてしまう。
当時、著作隣接権利者の定義が細部まで行き届いていなかったこともあり、シンセサイザーは身体に接合していないという理由で、楽器として認識されていなかったのです。しかし、90年代にPCが本格的に音楽に導入されることになり、シンセは電子音楽という特定のジャンルだけではなく、あらゆる音楽を制作するツールとして不可欠な存在になります。ここに、総合的に音楽を制作するというシンセの進化があるわけです。こういった流れを経てようやく、シンセサイザー奏者は紛れもなく演奏家だろうという評価になり、著作権、著作隣接権の定義が組み込まれ、ミュージシャン個人への分配が可能になったのです。
― 松武先生は大変にご尽力なさったわけですね。
松武:僕は現役でやっていることもあり、やはり後輩の育成の為にも、僕のような立場の人間が行政機関に対してきちんと発言をしていくべきだと思っています。テクノロジーの進化とともに、権利保護も変化していきますからね。
― そうですね、本当に電子音楽の進化は凄いです。
松武:現在DAW(Digital Audio Workstaion)の自由度は計り知れないほどの進化を見せています。テクノと歌モノの見事な融合を完成させたダフト・パンクやマドンナ、レディー・ガガなどは電子音楽を駆使した作品を発表し続けています。シンセが発明されてわずか約50年ですが、これからも更なる進化は続くと思います。
バックナンバー season 3
年別記事一覧